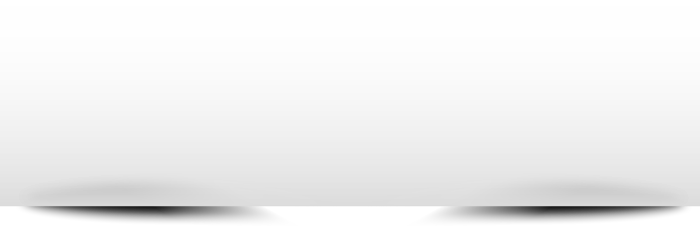宇部セントラルコンサルタント
山口県宇部市中野開作67番地
TEL.0836-41-6866(代表)
FAX.0836-41-2345

モバイルサイトにアクセス!
地域貢献
20220223 中川遊水池周辺の清掃活動を行いました
中川遊水池周辺には絶滅危惧種のヒヌマイトトンボが生息しております。
ひとたび、大雨が降ると上流域から大量のゴミが集積してきます。
これらのゴミを定期的に回収し、ヒヌマイトトンボの保全を図っております。
20211213 まじめ川でキャンドルナイトを行いました
引き続き、冬季もキャンドルナイトを行いました。
前回同様に、多くの方のご協力を頂きました。
このミズベリングでは、キャンドルの数を増やし、区間の延長、出店の拡大、さらに、スノーボード作りも行いました。
夕方より、シャボン玉のイベントも行い、多くの集客から歓喜が上がっていました。
次回は、2022年11月を予定しております。
20210313 まじめ川でキャンドルナイトを行いました
当社は宇部版ミズベリング研究会の会員として、宇部市を流れる真締川を対象としたキャンドルナイトを行いました。
本プロジェクトは、宇部市が推進する「ミズベリング・プロジェクト」の一環で、真締川の活用とにぎわいの創出を目的に行っているものです。
宇部大橋周辺に位置する犬の銅像のある河川敷や遊歩道を対象に、約3000個のキャンドルで彩り、来園者に明かりを堪能して頂きました。
開催に当たり、「宇部工業高等学校」「慶進高等学校」「株式会社FEEL」「琴芝地区自治会連合会」「上宇部地域づくり協議会」等、多数の方がキャンドルナイトの開催に携わって頂き、約1000名の集客を見込むことが出来ました。
しのざき宇部市長にも出席して頂き、点火式を行いました。
次回は、秋を目標に開催予定で、少しずつ、キャンドルで描く模様や数を増やしていければと考えているところです。
20201025オリーブ収穫祭
オリーブの収穫祭を行いました。
月2回の草刈りや樹木のメインテナンス作業を積み重ね、オリーブの実がたくさん出来るように頑張っています。
草刈りはヒツジやヤギにも手伝って頂くとともに、動物と触れ合うことでリフレッシュ効果を高めております。
収穫祭したオリーブは、参加して頂きました皆さんに持ち帰って頂いております。
今後は年1トンの収穫をめざし、オリーブ油の製造につなげたいと考えております。
オリーブの実は渋抜きを行った後に、塩漬け、ワイン漬け、サラダ、ピザなどに乗せて食べております。
椹野川河口干潟自然再生事業(アサリ調査-冬季2020)
椹野川河口干潟等では、産官学民の多様な主体の連携により「里海の再生」を目指した取組が進められております。
今年度は、冬季にアサリなどの二枚貝の調査に参画させて頂きました。
今回のコロラード調査では、アサリ、ニッコウガイをはじめスナモグリ、チゴガニ、ゴカイ類等が多く確認されました。
春先には潮干狩りのイベントを行うようです。